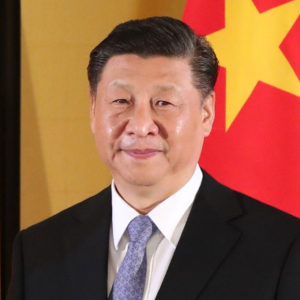参議院選挙で、自民党・公明党の与党連合が過半数を割り込む歴史的大敗を喫し、新興保守政党である参政党が躍進を見せた。この結果は、日本の政治地図に大きな変動をもたらし、隣国の韓国と中国でも注目を集めている。両国はそれぞれの国益と地域情勢の観点から、この選挙結果を独自の視点で解釈しているが、総じて日本の政治的不安定さと保守回帰の兆候に対する警戒感が浮き彫りになっている。
韓国では、自民党の大敗を「日本の政治的不安定化」と捉え、日韓関係の先行きに懸念を示す声が強い。自民党は長年、安定した政権基盤を背景に韓国との外交を進めてきたが、今回の敗北で石破茂首相のリーダーシップが揺らぐ可能性が指摘されている。特に、韓国メディアは参政党の「日本人ファースト」や反移民的な主張に注目し、これを「右翼的な動きの台頭」と表現。歴史問題や領土問題で対立が続く日韓関係において、保守勢力の伸長は融和的な対話の障害となり得るとの見方が広がっている。韓国政府は、尹錫悦政権下で日米韓の安全保障協力を強化してきたが、日本の政局混乱がこの枠組みに影響を及ぼすことを懸念。米国の対中政策や関税交渉とも絡み、日本国内の右派台頭が韓国の戦略に複雑な影響を与えると分析されている。
一方、中国は日本の選挙結果を比較的冷静に受け止めている。中国外務省は一貫して「日本の内政問題には干渉しない」との立場を表明しつつ、日中間の「戦略的互恵関係」の継続を求めるコメントを出している。しかし、中国メディアは参政党の躍進を「日本のナショナリズムの高揚」と分析し、警戒感を隠さない。特に、参政党が掲げる外国人受け入れ反対や歴史教育の見直しといった政策は、中国への対抗意識を反映していると受け止められている。中国は、日本が米国との同盟を強化しつつ、国内で保守的な動きが強まることで、東シナ海や台湾問題を巡る緊張が高まる可能性を注視している。ただし、自民党の敗北が直ちに日中関係に大きな影響を与えるとは考えていないようだ。むしろ、石破政権の弱体化が日本の対外政策の不透明さを増し、中国にとって交渉の余地を生むとの楽観的な見方もある。
両国の反応の違いは、それぞれの対日政策の優先順位を反映している。韓国は日韓の歴史的・感情的な対立を背景に、参政党のような勢力の台頭を直接的な脅威と捉えがちだ。一方、中国は地政学的・経済的な観点から、日本の政局変化を大局的に見る傾向にある。しかし、共通するのは、参政党の急伸が日本の保守層の不満と不安を吸収した結果であるとの認識だ。物価高や外国人増加への懸念、コロナ禍での陰謀論の拡散など、日本社会の分断を背景に、参政党は若年層を中心に支持を広げた。この動きは、グローバル化や多文化主義への反発として、韓国や中国にも通じるポピュリズムの潮流と重なる。
今後、日本の政局が不安定化すれば、韓国は日韓関係の停滞を、中国は地域の力学変化をそれぞれ注視するだろう。参政党の議席増は、日本の保守層の動向を映す鏡であり、両国にとって日本の内政が外交に与える影響を再評価する契機となる。石破首相が続投を表明したものの、与党の求心力低下は避けられず、参政党の動向が日中韓の三角関係にどう波及するかは、引き続き注目される。
(北島豊)