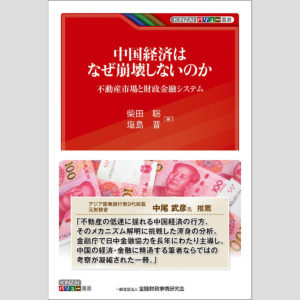中国は不動産不況で、もはや破綻状態であるという論が巷に溢れている。しかし、一向に破綻しそうにない。多くの中国人観光客が日本を訪れ、都心のタワーマンションは中国人に買い占められているという噂さえ聞こえてくる。
本書は、中国がなぜ大混乱に陥ることなく、安定した経済運営を維持できているのかを分析、解説する。 まずは「中国不動産市場の低迷と混乱」について。
恒大集団など大手デベロッパーの破綻が続いている。
中国のGDP(国内総生産)の3割が不動産関連である。事態を受けて中国政府は「保交楼」政策という、住宅購入者への物件引き渡し義務を政治的にコミットした。手厚いのだ。
大手デベロッパー破綻による国内混乱を回避するべく、政府はあらゆる手を尽くし、かつ国営デベロッパーを成長させる。政府の強力な関与で、ゆっくりと不動産不況は正常化に向かっていくという。
「不動産バブルの崩壊」については、こう言及する。私たちは日本の不動産バブル崩壊の記憶がいまだに生々しいが、この国は事情が違う。中国は国が広いから、不況に陥っている地域と、そうではない地域とが混在しているため、国全体が不況ではないのだ。人口も多く、潜在的な不動産需要が大きいため日本と同じと考えてはいけないのだ。
中国は、大手国有銀行が不動産会社に対して、不良債権を抱え込むプールの役割を果たしているという。日本のように不良債権を抱え込んだ銀行を破綻させたり、ハゲタカ外資系ファンドに売るようなバカな真似はしないのである。
金融システムの分析にも言及する。中国の銀行は、大手国有銀行の寡占状態である。不良債権比率は1.6%~3.8%である。日本のバブル崩壊時、大手銀行は8.4%の不良債権比率だった。このことを考慮すれば、中国の金融システムは総じて健全であるといえる。中国の大手銀行は国家機関であるため簡単に破綻させることはないのだ。政府主導で、この5年間で約300兆円もの不良債権を処理してきたという。なんという規模だ。日本は約100兆円だったので3倍である。
最後に著者は、不良債権の処理が終わるまで、中国経済の停滞は続くが、破綻はないと結論付ける。かつて、私は中国の財政責任者から、日本のバブル崩壊を学んでいると聞いたことがあった。この国は、日本のようにハードランディングではなく、ソフトランディングを試みているのだろう。中国のやり方を見ていると、なぜ日本はあれほどまでのハードランディングを行い「失われた30年」という経済低迷を招いてしまったのか、疑問に思わざるをえない。日本は、アメリカの策略に騙されてしまったのか。
《「中国経済はなぜ崩壊しないのか 不動産市場と財政金融システム」柴田聡・塩島晋・著/1650円(金融財政事情研究会)》
江上剛(えがみ・ごう)54年、兵庫県生まれ。早稲田大学卒。旧第一勧業銀行(現みずほ銀行)を経て02年に「非情銀行」でデビュー。10年、日本振興銀行の経営破綻に際して代表執行役社長として混乱の収拾にあたる。「翼、ふたたび」など著書多数。