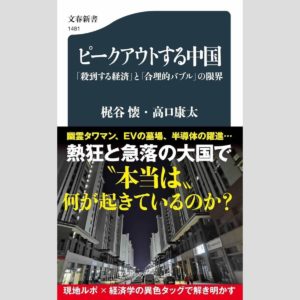中国経済については極端な悲観論と楽観論がある。長く続いた高成長はすでに止まり、やがて破滅に向かっていくしかないだろうという見方。いやいや、これからも成長は続いていくだろうという見方。
日産をはじめ日本の有名企業が次々と中国から撤退している。その一方で、例えば中国の電気自動車メーカーBYDの販売実績がホンダや日産を抜いたというニュースが流れだし、中国のAI、ディープシークがIT界の話題をさらった。格安かつ高性能で、既存AIの手強い競争相手となるだろうというのだ。
本書は不動産危機(悲観論)とEV急成長(楽観論)は、コインの裏表なのだという視点で現在の中国経済を分析する。
梶谷懐は経済学者で神戸大学大学院教授。高口康太は中国史研究からジャーナリストに転身した人で、千葉大学客員教授。マクロのデータ分析だけでなく、現地を取材しているのが特徴だ。複眼的分析である。
不動産バブルの崩壊をレポートする第1章が衝撃的だ。例えば、高口が目撃した天津市郊外の高級高層マンション団地。中央には世界一の高さの未完成ビルがそびえ立つ。ところが建設開始から7年後の2015年、デベロッパーが破綻して工事が止まり、野ざらしのまま10年たってしまったのだという。
そこには、予約販売によって資金を集めて、次のプロジェクトに着手するという自転車操業的なデベロッパーの事情が見える。自転車は止まると倒れてしまう。
では、なぜ自転車が止まるのか。著者らは「2020年を起点とするコロナ禍以降の財政金融政策の歪み、2014年を起点とする都市化政策の失敗、21世紀初頭から続く合理的バブル」という3つの問題を挙げている。
大雑把な言い方をすると、コロナ禍対応も含めて、政府のコントロールがうまくいかなかったということだ。
BYDのホンダ・日産超えが象徴するように、中国ではEVが絶好調。しかし「この強大な供給力によって生み出された生産物を、いったい誰に買ってもらうのか、という需要サイドの問題が取り残されている」と著者は指摘する。輸出しようとしても、相手国では反発も大きい。そういえば日本でもBYDのクルマをほとんど見かけない。
「供給能力が過剰で、消費需要が不足している」というのが、中国経済の根源的な問題だと著者は指摘する。「一帯一路」構想というものは、途上国・新興国に資金援助して成長を促し、ばんばん中国製品を買ってもらえるようにしようというものだった。
しかし、ことは目論見通りに進むとは限らない。資金援助を受けてもあまり成長せず、借金を返せなくなることもある。やっぱり自国の内需を増やすしかないのだ。
本書は中国経済についてのものだが、日本にもヒントとなることがけっこう多い。景気をよくするには、人びとがほしくなるものを作り、買えるようにしていくしかない。
《「ピークアウトする中国『殺到する経済』と『合理的バブル』の限界」梶谷懐・著 高口康太・著/1210円(文春新書)》
永江朗(ながえ・あきら):書評家・コラムニスト 58年、北海道生まれ。洋書輸入販売会社に勤務したのち、「宝島」などの編集者・ライターを経て93年よりライターに専念。「ダ・ヴィンチ」をはじめ、多くのメディアで連載中。