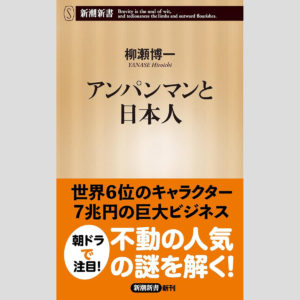「ださい‥‥」
初めてアンパンマンを見た瞬間、筆者は思わずそうつぶやいた。スーパーマンであれバットマンであれ「─マン」とつくヒーローはみんなかっこいい。ところが、アンパンマンは違う。あんパンそのものの丸顔で、体型もメタボ中年のよう。こんなキャラクターがウケるはずがない、と筆者は思った。
それから長い歳月が流れた。いま日本中の幼児たちはアンパンマンに夢中だ。泣いている赤ん坊もアンパンマンを見ると笑顔になる。そして「アンパンマン!」とまだ回らぬ口で叫ぶ。筆者の予想は外れたのだ。
なぜアンパンマンは大人気なのか。子供たちはアンパンマンのどこに魅了されるのか。どうしてアンパンマンの人気は続くのか。これらの謎について、考察したのが本書である。
手がかりは、作者・やなせたかしの人生、そして著者自身の子育て経験や「アンパンマンこどもミュージアム」などを訪れての見聞など。著者は、元編集者で現在は東京科学大学(旧称・東京工業大学)教授。「国道16号線」(新潮社)などの著書がある。やなせたかしと同姓であるが、親子でも親戚でもない。
アンパンマンの人気を予想できなかったのは筆者だけではないようだ。88年、テレビアニメが始まった時、テレビ局内では反対の声が少なくなかったという。月曜日の夕方5時という放送時間帯で、スポンサーもつかない。ゴーサインを出した幹部さえ、期待していなかった。ところが、放送を開始すると子供たちは大喜び。たちまち人気番組になっていった。実は元となる絵本も、出版社からは反対されたが、書店の売り場では子供たちに大人気ということが起きていた。つまり、テレビマンも出版社の編集者も、子供の心がよくわかっていなかったのだ。
本書を読んで痛感するのは、やなせたかしという人物の魅力である。彼は若い頃からマルチな才能を発揮してきた。絵も描くし、物語も作る。誰もが知る歌「手のひらを太陽に」(61年)の作詞も彼、サンリオから出ていた文芸誌「詩とメルヘン」の編集長も彼。
しかし、強烈な個性を持つ人ではなかった。悪くいえば器用貧乏で、それが彼の悩みだった。凡人は「オレはなんでもできる」と自惚れるが、やなせたかしは悩んだ。その苦悩がアンパンマンにつながる。幼い時から多くの別れと死を経験してきた人でもある。だからこそ、生きることの大切さを知っている。
アンパンマンの根底にあるのは「利他の精神だ」と著者はいう。アンパンマンは困っている人を助ける。見返りは求めない。人生はディール(取引)ではない。トランプにアンパンマンを見せてやりたい。
アンパンマンは人を助けるために自分を犠牲にする。それは簡単なことではない。しかし、アンパンマンを見て「世の中には自分を犠牲にしてでも助けてくれる人がいる」と感じた子供は、自分の未来に希望を持つだろう。なぜ子供たちがアンパンマンを支持するのか、その理由がわかった。
《「アンパンマンと日本人」柳瀬博一・著/968円(新潮新書)》
永江朗(ながえ・あきら):書評家・コラムニスト 58年、北海道生まれ。洋書輸入販売会社に勤務したのち、「宝島」などの編集者・ライターを経て93年よりライターに専念。「ダ・ヴィンチ」をはじめ、多くのメディアで連載中。