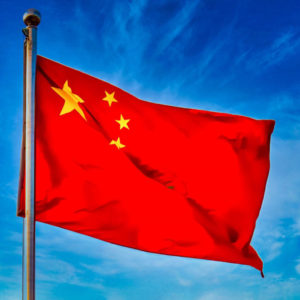中国には「盛世買骨董、乱世買金」ということわざがある。繁栄期には骨董品を買い、乱世には金を買えという意味だ。
中国の歴史は、戦乱と天変地異の連続だった。資産を守り増やすことが一族の運命を守る——それが中国人の考え方だ。改革開放の変化を見抜いた者は不動産長者になり、それに続いた一般の人も富裕層に仲間入りできた。
ところが中国で資産を運用するのは難しい。マンションも株も資本主義国とは異なる仕組みだ。土地は買うことができず、買えるのは土地の使用権で、それもせいぜい70年。株が暴落すれば「当局」は簡単に市場を閉鎖する。
つまり、人口14億の中国で17億戸ものマンションが計画され、株式市場が政府にコントロールされることを危ぶむ富裕層が、冒頭の格言にならい不動産や株式に見切りをつけて、骨董に力を注いでいるのだ。
筆者は中国で骨董ブームのはしりを体験したことがある。中国がWTO(国際貿易機関)に加盟した2002年のことだった。
アパレル工場の経営で大儲けした陳強軍(当時41歳)さんが趣味の骨董を勉強するために、明治時代に清朝の財宝を大量に買い取ったという古美術商の山中定次郎が発刊した清朝の骨董目録図書を探す手伝いをした。
清王朝が辛亥革命(1912年)で倒れると、最後の皇帝である6歳の「薄儀」に代わって「薄威」が清王朝の復活に挑み、その資金作りために300年続いた清王朝が蓄えた第一級の国宝を大量に売却した。それを買ったのが、世界的な古美術商として知られた山中定次郎である。
また、欧米の侵略に対抗すべく清朝政府とそれに続く中華民国政府は大量の留学生を日本に送った。資金源は美術工芸品だ。清王朝の貴重な美術工芸品を、日本に売却した。
だからいま、中国人の富裕層は日本で骨董を求め、「中国の国宝を買い戻した」と自慢し合う。なかでも有名なのが清朝第4代康熙帝時代に皇帝専用の窯である「官窯」で焼かれた「青華万壽尊」の歴史ヒストリーだ。
「青華万壽尊」は康熙帝を祝うために制作された気品に溢れた壺だ。高さが約70㎝、白地に青色で「壽」という文字が1万個整然と書かれたもので、中国歴代王朝の至宝の中でも超一級にランクされるものだという。
辛亥革命を経て日本に渡り、昭和天皇即位を記念した京都博覧会の出品目録に記載され、高名な収集家と知られた高島屋の祖である飯田新七が所蔵した後に所在不明となっていた。ところが地方のオークションに最低落札価格100万円で出品され、なんとそれを中国人が1億円で落札した。新たに所有者となった中国人のコレクターは「国宝を里帰りさせることができた」と自慢し、そして3カ月後、中国のオークションに出品して11億円で売却している。
こうした例は、ニューヨーク、ロンドン、香港、上海のオークションで頻繁に起こっている。
今年のGW4月29〜30日、世界のコインコレクターが注目する「東京コインオークション」がおこなわれた。注目は、英国の貨幣史を象徴するヘンリー7世の「ソブリン金貨」と、クラウン試鋳金貨の「スリーグレーセス」。前者の最低入札価格は1億円、後者は2500万円と驚異の価格でスタートすると伝えられ、世界の注目を集めていた。
ところが、世界をもっとも驚嘆させたのは前評判にも上らなかった中国・清の威豊帝時代の2つの「穴あき銭」だった。1つは最低入札価格5万円だったが、入札が始まるとアッと言う間にせり上がり、落札価格は2億円。さらに、2つ目の「穴あき銭」も1億3000万円で決まった。
2つの「穴あき銭」を落札したのは中国人。競りの間、代理人が本国のコレクターとひっきりなしにスマホで連絡をとっていた。パンダ金貨が数多く出品されていたが、これもほとんどを中国人が落札した。
この日の総売上は「東京コインオークション」史上初の20億円超えとなったが、そのほとんどは中国人によるもの。中国人富裕層の資金力に驚くばかりだ。
(団勇人・ジャーナリスト)