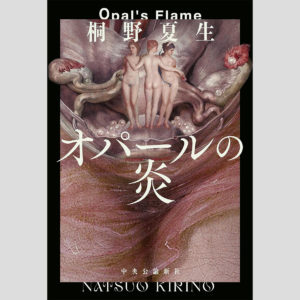「中ピ連」を覚えているだろうか。正式名称は「中絶禁止法に反対しピル解禁を要求する女性解放連合」。1970年代半に活動した団体である。今でいうフェミニズム、当時の言葉でいえばウーマンリブの団体だった。その名の通り、中絶の自由とピル解禁を訴えた。
しかし、彼女たちの活動はそれだけではなかった。不倫をする男の公開糾弾活動も行った。ピンクのヘルメットを被ってプラカードを掲げ、不倫男が勤務する会社に押しかけた。糾弾された男たちは、大いに恥ずかしい思いをした。
中ピ連騒動の時、筆者は中学生だったが、テレビのワイドショーも週刊誌も、彼女らの扱い方が微妙だったのを覚えている。嘲笑が半分で、その主張をまともに取り上げなかった。全共闘運動を模したとおぼしいヘルメットとプラカードというスタイルを含めて、キワモノ扱いだったのだ。
また、そのセンセーショナルな運動スタイルゆえに「フェミニズムに対する誤解と偏見を招いた、女性解放を推進どころか、むしろ後退させた」という批判もあった。
つまり、中ピ連は四面楚歌だった。
本書は、中ピ連を率いた榎美沙子をモデルにした長編小説である。作中で中ピ連は「ピ解同」に、榎美沙子は「塙玲衣子」に変えられている。もちろん、あくまでフィクションであって事実そのままではない。
小説に塙玲衣子自身は登場しない。今では、すっかり忘れ去られた存在になっている彼女について、若いライターが当時を知る人々にインタビューするという趣向だ。登場するのは、夫の不貞を糾弾した女や塙の元側近、塙を取材した週刊誌の編集長や記者、塙の幼なじみ、甥夫婦、義妹、そして元夫など。ピ解同に糾弾された男の家族も登場する。
周辺の人々が語れば語るほど謎は深まる。京都大学薬学部を卒業して薬事の専門家となり、医師と結婚した彼女が、なぜ過激な女性解放運動を始めたのか。なぜ政党を結成して国政選挙に候補者を送ったのか。なぜ塙・榎自身はその選挙に立候補しなかったのか。選挙で惨敗すると、なぜ専業主婦になったのか。単なる目立ちたがり屋だったのか。時代のあだ花なのか。やがて晩年の塙が残したノートが出てきて‥‥。
今振り返ると、榎美沙子と中ピ連が主張したことは時代の先取りだったのだとわかる。中絶についての意識も、ピルについての意識も、榎が主張したとおりになった。まだまだ不十分とはいえ、妊娠や出産について、女性の自己決定権を重視する考え方が突飛なものではなくなった。不倫糾弾にしても同様だ。
この半世紀で男女の関係はずいぶん変化した。今どき男尊女卑が正しいなどと思っている人はいない。ただ、そこから抜け出せない人は、まだ少なくないが。望まない妊娠について、男性の責任を問う声が大きくなっている。榎美沙子の不幸は、あまりにも早すぎたことかもしれない。
《「オパールの炎」桐野夏生・著/1870円(中央公論新社)》
永江朗(ながえ・あきら):書評家・コラムニスト 58年、北海道生まれ。洋書輸入販売会社に勤務したのち、「宝島」などの編集者・ライターを経て93年よりライターに専念。「ダ・ヴィンチ」をはじめ、多くのメディアで連載中。