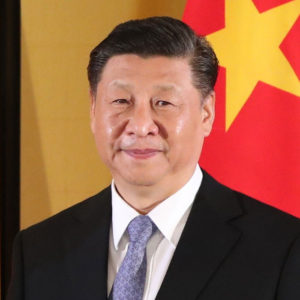沖縄県・尖閣諸島周辺における中国の動向は、近年ますます強硬さを増している。中国海警局の船やヘリコプターによる領海・領空侵犯、海洋調査船の活動、東シナ海での構造物設置など、一連の行動は日本にとって深刻な懸念事項である。これらは、中国が「サラミ戦術」と呼ばれる手法を用いて徐々に現状を変更し、実効支配を強めようとしていると分析される。
「サラミ戦術」とは、相手に大きな衝突を避けつつ、段階的かつ小刻みに利益を積み重ね、最終的に大きな目標を達成する戦略を指す。サラミソーセージを薄くスライスするように、少しずつ現状を変更し、相手が強く反発する前に既成事実を積み上げる手法である。中国の尖閣周辺での行動はこの典型例とされる。
具体的には、以下のような特徴がある。まず、小規模な挑発を繰り返す。中国は単発的な大規模侵攻ではなく、漁船や海警船による小規模な領海侵犯を頻繁に行い、日本の対応を試す。これにより、日本が軍事衝突を避ける傾向を利用し、徐々に中国のプレゼンスを強化する。
次に、既成事実の積み重ねを図る。海洋調査や構造物設置を通じて、尖閣周辺での活動を「通常化」させ、国際社会に中国の影響力拡大を既定路線として認識させる。最後に、相手の反応を観察しながらエスカレーションを調整する。
中国は日本の抗議や国際社会の反応を見つつ、行動の強度を調整し、全面衝突を回避しながら利益を最大化する。この戦術は、南シナ海での中国の行動にも見られる。南シナ海では人工島建設や軍事基地化を進め、周辺国が強く反発する前に実効支配を拡大した。尖閣でも同様に、領有権主張を裏付ける活動を積み重ね、日本の実効支配を揺さぶる狙いがある。
中国の「サラミ戦術」は、日本にとって複数の課題を突きつける。まず、領海・領空侵犯の頻発は、日本の防衛リソースを圧迫する。海上保安庁や自衛隊は常時対応を強いられ、人的・物的負担が増大する。また、中国の行動は日中関係の緊張を高め、外交的解決を困難にする。中国が「日本の不法侵入」と主張することで、国際社会における日本の立場を揺さぶる意図も見られる。
国際社会への影響も大きい。中国の行動は、東シナ海の航行の自由や海洋秩序に挑戦するものであり、米国やオーストラリアなど同盟国との連携が不可欠となる。日米安全保障条約に基づく米国の関与も焦点だが、中国の段階的アプローチは、米国が軍事介入する明確な「レッドライン」を引きにくい状況を作り出している。これにより、地域の安全保障環境は不安定化し、近隣諸国への波及効果も懸念される。
日本は、海上保安庁の巡視強化や自衛隊の警戒監視活動を通じて、尖閣の実効支配を維持する姿勢を堅持している。外交面では、中国への抗議を繰り返し、国際社会に問題の深刻さを訴える努力を続けている。しかし、「サラミ戦術」の巧妙さに対し、単なる抗議や現状維持では限界がある。国際法に基づくルール重視の海洋秩序を強調し、米国やASEAN諸国との連携を深めることが求められる。また、国民への情報開示や国際世論の喚起も重要だ。
(北島豊)