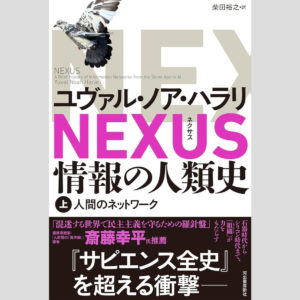世界的ベストセラー、「サピエンス全史」や「ホモ・デウス」(共に河出書房新社)で知られるユヴァル・ノア・ハラリの新著である。
人類の歴史を情報ネットワークの歴史として読み直す。上巻「人間のネットワーク」と下巻「AI革命」からなる。巻末の註や索引を除いて500ページを超えるが、文章は極めて平明。タイトルの「NEXUS」は、英語で「結びつき、関係、つながり」を意味する。
なお、ハラリはイスラエルのヘブライ大学教授だが、ネタニエフ政権によるガザのジェノサイドについて厳しく批判している。ネタニエフはイスラエルを守るどころか、むしろ危険にさらしている、というのだ。
さて、情報といえば、ひところ「情弱」という蔑称が流行したことを思い出す。情報弱者の略である。しかし、この言葉の前提には、情報というものに対してナイーブな信頼がある。「情報は常に正しく、情報は多ければ多いほど良い」という。果たして本当だろうか。
「サピエンス全史」においてハラリは、人類を進歩させた原動力は、見知らぬ者同士の協力だといい、その協力の鍵となるのが虚構だと指摘した。虚構もまた情報。虚構は神話、宗教の聖典、あるいはイデオロギーと読み替えてもいい。
象徴的なできごとが印刷革命と魔女狩りだ。15世紀の半ば、グーテンベルクが活版印刷を発明した。これによって科学革命が起きたといわれる。だがそれだけではなかった。魔女狩りもこの時期に大流行した。魔女についての情報も印刷技術によって広まり、多くの人が「魔女・魔法使いだ」とされて処刑された。魔女狩りに熱狂した人たちは、情弱だったろうか。むしろ情報の過多が彼らを結びつけ、煽り立てたのではないか。
新聞が普及したり、ラジオが登場したり、情報の新技術が次々と登場した。しかし、ドイツの人々はヒトラーの演説に陶酔し、ソ連の人々はスターリンを崇めた。人類の強みは「間違えたら直す」という自己修正のメカニズムだが、宗教やイデオロギーは誤謬を認めない。情報があればいいというものではないのだ。
この本の主眼はAIについての批判的検討である。「AIはこれまでの情報テクノロジーとは違う」とハラリは指摘する。なぜなら、AIは自ら決定し、新しいものを生み出すからだ。そこが印刷機やラジオ、テレビとは違う。AIは人間が作ったデータをむさぼり食い、アルゴリズムによって生成し、拡散する。データの中には、誤りもあれば偏りもある。それが猛スピードで増殖していく。
〈もし私たちが扱いを誤れば、AIは地球上の人間の支配に終止符を打つばかりか、意識の光そのものも消し去り、宇宙をまったくの闇の領域に変えてしまいかねない〉とエピローグでハラリは警告する。
息を吐くように噓をつく男がアメリカ大統領になり、巨大IT企業が彼の前にひざまずく時代、ハラリの言うことがまったくの杞憂とは思えない。
《「NEXUS 情報の人類史 上:人間のネットワーク 下:AI革命」ユヴァル・ノア・ハラリ・著 柴田裕之・訳/各2200円(河出書房新社)
》
永江朗(ながえ・あきら):書評家・コラムニスト 58年、北海道生まれ。洋書輸入販売会社に勤務したのち、「宝島」などの編集者・ライターを経て93年よりライターに専念。「ダ・ヴィンチ」をはじめ、多くのメディアで連載中。