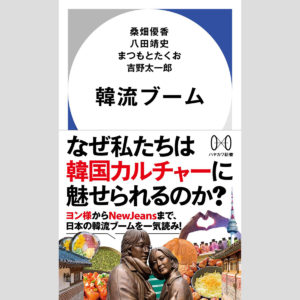1988年まで韓国では映画、アニメ、漫画、ポップスなど日本の大衆文化を持ち込むことが禁止されていた。それが段階的に解除され、現在のように往来自由になったのは04年である。若い人はもちろん、年配者でも知らない人は多い。
なぜなら、当時は日本国民のほとんどが韓国文化への関心を持っていなかったからだ。チョー・ヨンピルの歌「釜山港へ帰れ」(83年)や、映画「シュリ」(99年)が日本で大ヒットしたものの一過性のものでしかなかった。
ところが、韓国での日本大衆文化が全面解禁になった途端、NHKで「冬のソナタ」(04年)が放送され、韓流ブームと呼ばれる一大潮流が生まれた。文化とは、相互交流して初めて深く、理解されるのかもしれない。
そんな現在へ至るまでの流れを克明に追ったのが本書だ。韓国食文化研究の第一人者、ジャーナリストとして韓国を観てきた者など、うってつけのメンバー4人が揃い、座談形式で進めていくから読みやすい。
初動から08年頃までの第1次ブームは主にドラマと映画に牽引され、そこで描かれる生活ぶりへの関心から韓国料理が急速に普及していく。なるほど、新大久保界隈がコリアンタウンと呼ばれるようになり、本格的な韓国料理店、カフェ、グッズ販売店が建ち並んだのはその頃だ。
10年~12年頃の第2次ブームはK-POPの力だ。KARA、少女時代というオジサン世代でもその名を知るアイドルが日本デビューし、東京ドームを満員にする勢いを示した。年配者向けには韓流時代劇ドラマが広がる。酒飲みのご同輩には、各種マッコリが入ってくるようになった話題に興味を持つだろう。
しかし、ここで大きな障害が出現する。12年、イ・ミョンバク大統領が、日本領ながら韓国も領有を主張する竹島に突如、上陸を敢行。一気に政治的緊張が高まり、当時の安倍政権との間に「最悪の日韓関係」と呼ばれる状態となった。政治が文化交流を引き裂いたわけだ。しかし、両国の国民は負けなかった。17年には第3次ブームが始まる。これが、SNSのインスタグラムの影響だとする分析は面白い。気軽に国境を越えて往来するようになった若者たちの「インスタ映え」する画像がきっかけになっているという。
そして20年~23年のコロナ期における第4次ブームだ。これは記憶に新しい。ネット配信ドラマで「愛の不時着」「梨泰院クラス」「イカゲーム」などが圧倒的人気を誇り、23 年の紅白歌合戦には7組のK-POPグループが出場した。
もはや「ブーム」ではなく日常的に定着した、というのが本書の結論である。われわれも著者たちが語る韓国文化の魅力を知り、もっともっと楽しもうではないか。
《「韓流ブーム」桑畑優香・八田靖史・まつもとたくお・吉野太一郎・著/1078円(ハヤカワ新書)》
寺脇研(てらわき・けん)52年福岡県生まれ。映画評論家、京都芸術大学客員教授。東大法学部卒。75年文部省入省。職業教育課長、広島県教育長、大臣官房審議官などを経て06年退官。「ロマンポルノの時代」「昭和アイドル映画の時代」、共著で「これからの日本、これからの教育」「この国の『公共』はどこへゆく」「教育鼎談 子どもたちの未来のために」など著書多数。