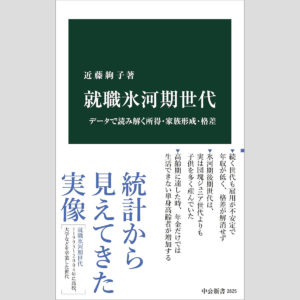本書によれば、就職氷河期世代とは、バブル崩壊後の景気後退が、新卒採用に大きく影響を及ぼし始めた1993年度の新卒者に始まる。詳しく見ると、93年度新卒から98年度までの6年が氷河期前期世代、99年度新卒から04年度までの6年が後期世代と呼ばれている。すなわち現在40代半ばから50代半ばにあたる年齢だ。皆さんも、自身がそうだったり、周囲に該当者がいたりする方がほとんどだろう。なにしろ、約2000万人、全人口の6分の1を占めているのだ。
この世代が、さまざまな形で不利を被り、社会の中で厳しい状況に陥っている者を多く抱えていることは広く知られている。ただ、その実情やバックにある問題をきちんと理解しておかないと、漠然としたイメージで「不運だったね」の同情で終わったり、「自己責任だろう」で済ませてしまったりすることになりかねない。
本書では、自らも氷河期世代だという気鋭の経済学者が、この世代がこれまでどんな運命を辿ってきたか、そして、このままだと今後どういう人生を歩むことになるかを、細密なデータ分析を通して明らかにしていく。まず、氷河期以前の世代との、年収格差が縮まらない実態が具体的に示され、改めてその深刻さを認識させられた。
だが、だから結婚や出産が難しくなり少子化が進んでしまったのか、とのありがちな解釈には明確な反論が示される。以前の世代と比べれば、産んだ子供の数は多い。この分析の手際はみごとだ。若い年齢同士で比較すると、晩婚化や女性の社会進出で少なく見えるものの、40歳までの出産という当節の在り方からすれば決してそうでなく、むしろ、バブルの恩恵を受けた世代を上回る。これには、目から鱗だった。
ただ、氷河期の影響をもろに受けた年収の少なさや就業率の低さは、いつまでも克服できていない。「これほど多数存在するこの世代が、マンパワーとして十分に活用されないまま終わってしまうのは、経済全体にとって大きな損失だ」との主張には、誰しも耳を傾けざるを得まい。
また、親に依存して生活する者が少なくないだけでなく、一般的に低年金・低貯蓄の傾向が強い彼らが老いていく場合の社会保障を、果たして国全体が支えきれるか─と迫る問題提起も痛烈だ。
読み進めると、終章において著者が提案する、いくつかの対策に賛同したくなる。就労しているのに十分な収入を得られない層への経済的支援、親の介護を支えざるを得ない者への、労働と両立できるような介護サービスの拡大は、いずれも重要だ。氷河期世代が生活破綻しないよう支えていくのは、実のところ、それ以外の世代にとっても極めて重要な意味を持つ。これは決して特定の世代だけの問題ではないのである。
《「就職氷河期世代 データで読み解く所得・家族形成・格差」近藤絢子・著/968円(中公新書)》
寺脇研(てらわき・けん)52年福岡県生まれ。映画評論家、京都芸術大学客員教授。東大法学部卒。75年文部省入省。職業教育課長、広島県教育長、大臣官房審議官などを経て06年退官。「ロマンポルノの時代」「昭和アイドル映画の時代」、共著で「これからの日本、これからの教育」「この国の『公共』はどこへゆく」「教育鼎談 子どもたちの未来のために」など著書多数。