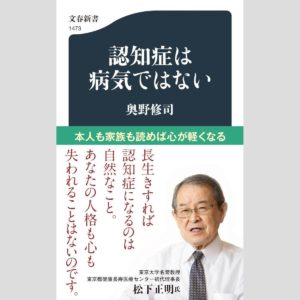本書は、兄の若年性認知症を契機に、認知症に興味を抱いたジャーナリストが「認知症の人の心の裡を知りたい」と取材を重ね、執筆した。著者は、島根県出雲市にある重度認知症高齢者のデイケア施設「小山のおうち」に向かう。ここで彼は認知症に対する認識を一変させる経験をする。
この施設には他の施設とは違うルールを高橋幸男院長が定めている。一つは「物忘れを認め合うこと」だ。ここでは「物忘れが上手になりまして」と挨拶する。もう一つは認知症患者が、歌ったり、思い出を語りあったりすると皆が拍手で称賛すること。すると、人は嬉しくなり、生きていることを実感する。院長は、認知症の人に手記を書いてもらっていると言う。
認知症の人は「また忘れて!」と注意されると「怒られた」と思ってしまう。EQ(心の知能指数)は正常なので、負の感情だけが残る。それで居心地が悪くなり「徘徊」という形で家を出てしまうのだ。著者は、認知症になっても心の裡には「私たちと同じ豊かな感情が溢れている」ことに気づく。
認知症は病気なのか、と著者は疑問を抱く。認知症になると、自分の置かれている状況が理解できない「中核症状」と徘徊や暴言の「周辺症状」があらわれる。著者は「周辺症状」を改善するためには、認知症患者のEQは私たちと同じであると理解し、その症状が彼らのSOSサインだと考えることを提唱する。
本書では「徘徊」という「周辺症状」がなくなった事例を紹介する。認知症で恐妻家の94歳の夫は、90歳の妻から「ボケェ」と言われ続け、ケンカが絶えなかった。夫は、それが辛くて「徘徊」を頻繁に繰り返していた。しかし妻は認知症の勉強会に行き、理解を深めた結果、夫に優しく「ありがとう」というようになった。すると夫も「食事がおいしかったよ」と答えるようになった。すると、夫の「徘徊」がなくなったのだ。夫は、妻が優しくなったお蔭で「居場所」を見つけることができたからなのだろう。
著者は、専門医の見解を踏まえ、高齢者の認知症は「病気ではない」という。耐用年数が過ぎれば、問題が起きるように、脳も神経細胞も耐用年数を過ぎた結果、認知機能の低下が起きるのだ。認知症は、高齢化したら誰にでも訪れる老化現象なのである。このことを理解すれば、認知症になっても安心して、当たり前に生きていける社会になるのではないかと著者は期待する。
本書は、医者という高邁な目線ではなくジャーナリストという立場で、私たちと同じ目線に立ち、認知症の課題を一つ一つ丁寧に解決しようと試みているのが、非常に新鮮である。
認知症に新たな視点を提供する本書は、高齢者及び高齢者を抱える家族に広く読むことを薦めたい。
《「認知症は病気ではない」奥野修司・著/1166円(文春新書)》
江上剛(えがみ・ごう)54年、兵庫県生まれ。早稲田大学卒。旧第一勧業銀行(現みずほ銀行)を経て02年に「非情銀行」でデビュー。10年、日本振興銀行の経営破綻に際して代表執行役社長として混乱の収拾にあたる。「翼、ふたたび」など著書多数。