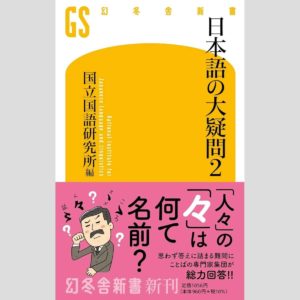国立国語研究所は、文部科学省が所管する国語に関する研究機関である。平たく言えば、日本語についての最高の権威を有する研究所だ。文化庁勤務時代、このお堅い機関を監督する立場にあったわたしは、そこに蓄積された豊富な知識を国民にわかりやすく伝えることができればと思ったのだが、実現できないままに終わっていた。
それが、幻冬舎の働きかけに応じ、新書の形で日本語に関するさまざまな疑問に答える本を作る運びとなったのは、個人的にもうれしい。21年に出した「日本語の大疑問」は大好評を博し今回続編の登場である。
最初の問いは「上から目線」の「目線」は昔からある言葉ですか?
回答は、昔からあるにはあったが、現在の意味だと80年余り前、映画製作現場の業界用語として使われ始めたらしい。俳優の演技を指示する時のものが、しだいに一般化し、70年代半ばには辞書にも載るほどになったそうだ。それが「その立場からの見方、視点」との意味にもなっていき、08年の調査では「庶民の目線で考える」という用法を7割以上の国民が認めている。
こんな調子で、場合によっては、図や表を使いながら専門家がわかりやすく解説してくれるのだ。例えば、船の名前に「〇〇丸」が多いのは、古代から奈良、平安時代に男性の人名に用いられた「麻呂」(例・阿倍仲麻呂)が、室町時代にマロからマルへ語形が変化して、豊臣秀吉の幼名「日吉丸」のように愛称となって一般化したのが由来‥‥といった具合に謎が解けていく。
何より驚かされたのは、「ムショ帰り」のムショの語源だ。てっきり刑務所だと信じ込んでいたのに、江戸時代の牢屋を指す隠語「むしよせば」(表記は虫寄場と六四寄場の両説)からのもので「監獄」を「刑務所」に改めた1922年より、ずっと前からあった言葉だった。
回答を執筆しているのは、いずれも国語研究所と関係の深い研究者の方々だ。真面目な解説の中に、自身の体験を白状する部分があったりして人間味を感じさせる。学級を示す「組」の読みが「くみ」と「ぐみ」があるのはなぜ? と小1の息子に問われ、専門家でいながら、すぐには説明できなかった失敗を告白。その後「ももぐみ」「たんぽぽぐみ」は、本来2つの名詞が結合している「複合語」なので後ろの語が濁音化する。それ対し、「1組」「2組」は、学級の数を数えるための「数詞」意識が働き「複合語」扱いされていないのではないか、と分析する。
なにしろ「ムショ帰り」なんていうアブナイ言葉が扱われるのが、型破りではないか。楽しく読める堅苦しさのない国語問答の本だ。
《「日本語の大疑問2」国立国語研究所・編/1056円(幻冬舎新書)》
寺脇研(てらわき・けん)52年福岡県生まれ。映画評論家、京都芸術大学客員教授。東大法学部卒。75年文部省入省。職業教育課長、広島県教育長、大臣官房審議官などを経て06年退官。「ロマンポルノの時代」「昭和アイドル映画の時代」、共著で「これからの日本、これからの教育」「この国の『公共』はどこへゆく」「教育鼎談 子どもたちの未来のために」など著書多数。