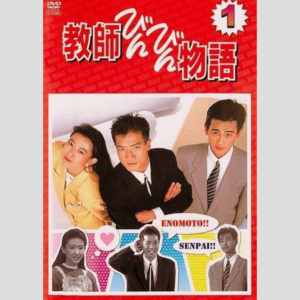テレビ黄金期だった昭和の時代。世代や性別を超えた視聴者をトリコにした大ヒットドラマが続々と生み出された。数々の名作に秘められた「裏テーマ」をテレビ解説者の木村隆志氏が語る。
78年から日本テレビ系で放送された「西遊記」は中国の古典小説を題材に、堺正章(76)が孫悟空を、故・夏目雅子(享年27)が三蔵法師を演じて人気を集めた。沙悟浄役の岸部シロー(享年71)、猪八戒役の西田敏行(75)も含めてキャスティングは錚々たる顔ぶれで、本来は男性であるはずの三蔵法師を美人女優が演じることでも、オリジナルにない魅力を引き出したものだ。木村氏は「昭和の社会の縮図を感じさせる4者の人間模様」が見どころだったという。
「やんちゃなヤツがいれば、ずる賢いヤツ、食いしん坊なヤツもいて、まるで当時の会社のようでした。絶世の美女の坊主にしても聖人と言いつつ、見方を変えると部下の頭に輪っかをつけて拘束し、無理やり言うことを聞かせるパワハラ上司のようなところもある。そんな個性豊かな面々が、今では考えられないどぎつい悪口やののしり合いをしながら、最後には力を合わせて勝つという、単なるヒーローものではないブラックな部分が面白かったですね」
昭和ドラマだからこそまかり通った〝ブラック演出〟という点では、フジテレビ系で放送された杉浦幸(53)主演の「ヤヌスの鏡」(85年)も視聴者に大きなインパクトを与えた。
「昭和といえば大映ドラマと言えるほど個性的な作品がたくさんあるのですが、その特徴の1つとしてまだ誰も知らないような新人の子をいきなり主演に据えるという手法があった。それに加えて、この作品に関しては二重人格の子を演じさせるという危うさがあり、ハラハラしながら見ていましたね」
作品に一貫する徹底した「無茶ぶり」には、とにかく驚かされたという。
「デビューしたてのアイドルにものすごい不良役を演じさせたばかりか、厳しい祖母から折檻されるというハードすぎる演出。〝毒母〟ならぬ〝毒祖母〟と孫娘の危うい関係が最終回まで延々と続いていく。杉浦さんはこの作品からわずか半年後、2作目の主演ドラマ『このこ誰の子?』(フジ系)でいきなり男に乱暴される役を演じるわけですが、女優デビュー早々、立て続けに強烈な演出に攻められすぎた結果、その後の女優人生に狂いが生じたのではないでしょうか」
人気絶頂の田原俊彦(62)が小学校の教師に扮した学園ドラマ「教師びんびん物語」(88年、フジ系)についてはこう振り返る。
「一世を風靡した初期の〝月9ドラマ〟で、いわゆる昭和の熱血教師ものです。熱血といえば聞こえはいいですが、意地悪な見方をすると生徒に干渉しすぎで、モンスターペアレントならぬモンスターティーチャー。小学校が舞台なだけに余計にその点が際立ち、実在したらきっと親も怒るでしょう(笑)」
同ドラマは、田原演じる徳川龍之介と野村宏伸(57)扮する後輩教師の榎本英樹による、コンビでのやり取りが人気を博した。
「今ではバディものがしばしばありますが、当時はここまで男同士の関係にスポットを当てる作品が珍しかった。そうした中で『この2人はどこまで仲がいいんだ』『榎本は徳川のことが好きなんじゃないか?』といった、今で言うBL(ボーイズラブ)的な見方ができました。2人とも若くてかっこいいですし、自分からガンガン行動しちゃうトシちゃんと、とことん受身の野村さんの対比がBLによくありがちなドSとドMの設定にもなっていた。うっすらとヒロイン的な存在はいたものの、当時のドラマとしては珍しく、それほど恋愛の流れにならなかったことも余計にBLっぽかったですね」
同じフジの月9枠で88年に放送された「君の瞳をタイホする!」の裏テーマはずばり「これも刑事ドラマ」である。
「元祖トレンディードラマと言われる作品で、出演者の陣内孝則さん(64)や柳葉敏郎さん(62)、三上博史さん(60)、それに久保田利伸さん(60)の主題歌も含めて映像から歌からすべてがかっこよかった。トレンディードラマを形作っていく雰囲気がひしひしと感じられたのですが、どうして設定が刑事ものなのかと大いに疑問でした。ヒット作ですし、覚えている人は多いでしょうが、刑事ドラマだったという認識は薄いのではないでしょうか」
舞台は東京・渋谷の道玄坂警察署を中心としていたが、作中では若い刑事たちのアフター5や恋愛模様が中心に描かれている。
「刑事たちがナンパしたり、コンパしたり、飲み会に行ったりで、刑事ドラマらしいシーンはほぼなく、逆にそうした場面を探すのが面白かったほどです。陣内さんも番宣などで『こんな刑事ありえないですよ』とこぼしていましたが、ここまでふざけた作品はなかったですよね」
昭和の名作ドラマの数々は「迷作」としても視聴者の心の中に残り続けているのである。
*週刊アサヒ芸能3月30日号掲載