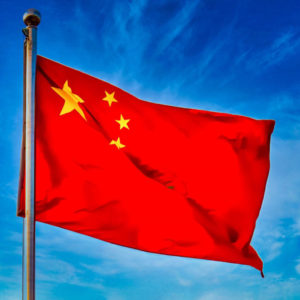近年、中国海軍の空母「遼寧」「山東」の太平洋進出が顕著になり、国際的な注目を集めている。特に今年6月には、これら2隻が日本近海で同時展開し艦載機の発着を繰り返すなど、過去に例のない活発な活動を見せた。この動きは、日本の防衛体制に強い圧力をかけるとともに、偶発的な衝突が日中間の全面戦争に発展するリスクを高めているとの懸念が強まっている。
中国海軍は、空母「遼寧」と「山東」を中心とした艦隊を、沖縄や小笠原諸島周辺の太平洋に展開。防衛省によると、25年6月7日から9日にかけて、「山東」から発進したJ15戦闘機が海上自衛隊のP3C哨戒機に異常接近し、最接近時はわずか45メートル、40分から80分にわたり追尾する事態が発生した。さらに、「遼寧」が米国の防衛ラインである「第2列島線」(日本からグアムに至る線)を越えて活動したのは初の事例であり、中国の海洋進出の意図を明確に示している。
中国の狙いは、太平洋での軍事プレゼンス強化と、日米同盟への牽制だと考えられる。中国共産党系メディア「環球時報」は、これらの活動が国際法に適合し、米軍や日本の監視活動こそが問題だと主張している。一方、専門家は、中国が空母運用能力の向上を通じて、西太平洋の覇権確立を目指していると分析する。最新空母「福建」の年内就役も予定されており、その電磁式カタパルト技術は、米国の空母に匹敵する能力を持つとされる。この技術進化は、中国海軍の遠洋作戦能力を飛躍的に高め、近隣諸国にさらなる脅威を与えている。
特に問題視されるのは、前述のような艦載機の異常接近だ。過去にも、14年に中国軍機が東シナ海で自衛隊機に30メートルまで接近する事例があり、挑発行為は繰り返されている。こうした行動は、偶発的な衝突を引き起こす可能性を高める。一旦衝突が起きれば、双方の軍が「相手が先に攻撃した」と主張し、報復の連鎖が戦争に発展するシナリオは、確率の問題として無視できない。
しかし、日本の防衛体制は太平洋側での警戒監視に限界があり、硫黄島や北大東島へのレーダー配備が進められているものの、中国の能力向上のスピードに追いついていない。一方、中国は空母艦隊の展開に加え、055型駆逐艦などの先進的な戦闘艦を配備し、米海軍に次ぐ規模の海軍力を誇る。
米国が西太平洋でのプレゼンスを弱める中、中国の活動は一層大胆になっているとの見方もある。日米同盟は依然として強固だが、トランプ政権下での米軍の動向次第では、日本の防衛負担が増大する可能性がある。もし衝突が起き、日本が単独で対応を迫られた場合、迅速なエスカレーション制御が困難になり、日中間で再び戦争が勃発する恐れもあるのだ。
(北島豊)