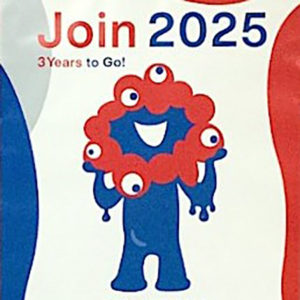せっかく手に入れた入場券で大阪・関西万博に足を運んだのに、「展示予約」や「飲食店予約」が、いつのまにか「高額チケット」に変わっていたら…。
無料で取得できるはずのパビリオンや飲食店の予約枠が、オンラインオークションやSNSで数千円に吊り上げられ、転売されるケースが相次いでいる。
中でも象徴的なのが「イタリア館」の予約枠だ。ルネサンス期の名画や最新AR体験を無料で楽しめる同館は大人気だが、その入場予約QRコードが、チケット売買サイトで2000円超という価格で出回っている実態が明らかになったのだ。担当者は「万博の趣旨に反する」と苦言を呈し、対策を要請している。
また、フードコートの看板店とも言える「くら寿司 大阪・関西万博店」でも予約枠の転売が横行している。QRコードがSNSで1000円~2000円で売買されている事例が確認されており、くら寿司側も「この予約を購入することも利用規約の不正行為に
SNSでも《転売行為を全面禁止し、発覚次第厳罰を科すべき》といった意見が多数寄せられている。
では、なぜこのような異常事態が起きたのか。最大の原因は、予約システム上の「穴」だ。現在のQRコード方式では、一度取得したコードを第三者に転送、コピーできてしまい、誰でも同じコードで入場できる。万博IDとQRコードが紐づいておらず、当日の会場チェックもQRスキャンのみ。こうした「本人認証」を伴わない運用が疑問視されている。
「転売を防ぐための対策も提案されています。まず、予約QRコードの読み取り時に『会員パスワード』や『生体認証(顔認証など)』の入力を必須とし、コードと本人を結びつける多要素認証を導入すること。これにより、画面キャプチャや他者への転送を無効化できます。さらに、ワンタイムQRコードや、入場時に会場スタッフによるID確認(QR+顔写真付き証明書)を組み合わせれば、不正使用の抑止力が飛躍的に高まるでしょう」(社会部記者)
今回の万博予約枠転売問題は「デジタルチケット社会」の盲点を突く事件ともいえる。来場者全員が安心してパビリオンもグルメも満喫できるよう、行政・運営側には、転売禁止のルール強化だけではなく、システム設計の根本的な見直しと、実効性ある運用監視が求められている。
(ケン高田)